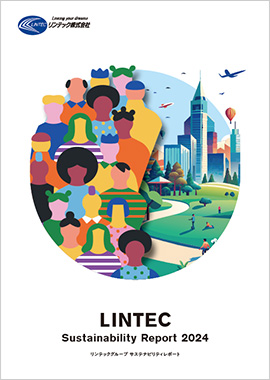- 小
- 大
ページ印刷
トップメッセージ

地道な取り組みを重ねてサステナブルな企業へ
施策を計画どおり推し進め、不足や至らない場合はすぐアクションを起こす
「LSV 2030-Stage 2」初年度を振り返ると、これまで身につけた困難な環境下でも果敢にチャレンジする底力でサステナビリティに関わる諸施策を推進できたと考えています。なかでもCO2排出削減はStage1に当初目標を前倒しで達成できたことから、さらに高い目標を設定し新たなアクションの検討・追加を進めています。また働き方改革の推進では人材に関する制度・仕組みを着実に整え浸透を図ったことで、積極的に活用されるようになってきました。
分かりやすい成果が出るまで時間を要している施策もありますが、繰り返し続けていけば壁を越えられると信じており、サステナブルな企業を目指して着実に進んでいると評価しています。
- ※株主・投資家情報ページ内に移動します。
自分しかできないことへ時間やパワーを使い、
働きがいのある職場へ
DXを駆使することで、仕事のやり方そのものを見直す
重要施策の一つであるDX*による各種の変革は前倒しで進んでおり、遠くない時期にリンテック流のDXが目に見える形になると楽しみにしています。この施策はAIやロボティクス技術を使って設計・開発・製造・物流などあらゆる業務プロセスを変革し、日々の仕事の効率や信頼性を高めることが本来の目的です。今日までベストなやり方だったとしても明日にはベストではなくなっているかもしれない、そう考えてDXの推進をサポートしています。この根底には業務を効率化・自動化して負担を減らし、従業員には自分しかできないことや自分がやりたいことに時間やパワーを最大限使ってほしいという思いがあります。
従来の仕事のやり方を肯定的に見直し新たなツールや手法を前向きに取り入れ積極的にチャレンジしていくことで、これからの社会に必要な働きがいのある職場環境をつくっていきます。
- *DX:Digital Transformationの略語。ビジネス環境の変化に対応するためにデータとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務の内容やプロセス、組織、企業文化などを変革し、競争優位性を確立すること。
制度や仕組みを積極的に活用し、継続的に改善する
働き方改革の推進では従業員が明るく生き生きと仕事に取り組むことで、顧客満足度や生産性の向上につながる制度や仕組みを整えました。データ上は順調に活用されていますが、使いづらいあるいは分かりにくいと感じているケースを逃さず把握し、改善していくことが重要です。社内の制度や仕組みは100点満点を目指していますが、今100点でも将来も100点を維持できるかというと、それは違うと考えています。当社を取り巻く経営環境は常に同じではなく、変わっていくからです。その変化の兆しを捉えて自分たちでもっと良い会社にしていくために、従業員一人ひとりが上司や同僚・同期と自由に話し合い率直に意見交換できるコミュニケーション環境の充実を図っていきます。

相手としっかり向き合い、受けとめる
コミュニケーションを取り、フィードバックをかける
私が初めて事業部門長になった時に所属員一人ひとりと面談しこれから担ってほしい役割を伝え、一方では私や部署への要望を聞いたことがありました。一週間近く時間を要しましたが、私の考えを伝えて相手の行動を引き出せたと考えています。この経験からコミュニケーションを取りフィードバックをかけることは、日々の業務で成果を出すことと同じく大切だと考えるようになりました。
私は普段から「コミュニケーションを大切にしてほしい」と言い続けていますが、私自身まずは相手としっかり向き合い受けとめたうえで自らの考えを伝えるよう意識しています。
気兼ねないコミュニケーションから意外なアイデアを生み出す
施策を計画どおり推し進め目標を達成できていても、現場では「もう少しやり方を変えたらもっと成果が出るのに」とか「このやり方だと負荷がかかり過ぎる」などの声が出てくるかもしれません。マネージャーが現場の声を確実に捉えてしっかりフィードバックをかければ、結果だけでは見落としてしまう気づきやヒントを得られる可能性があります。会議など業務上のやりとりに加え、雑談など気軽なやりとりにもひらめきがあるかもしれません。従業員同士がもっと自由にコミュニケーションすれば意思疎通と情報伝達がさらに良くなり、長期ビジョン実現に役立つ当社らしいアイデアが絶えず出てくると考えています。
変えていくこと、そのアクションこそがイノベーション
真正面から立ち向かうだけでなく、ずらして深掘りする
長期ビジョン実現やそのマイルストーン達成に取り組む過程では、課題解決に真正面から立ち向かい深掘りしても打開できない状況に陥ることがあると思います。打開できない事実を解消するには、改めて課題を解析して解決するためのアイデアを何通りも持って突き進むことが必要です。これを私は“ずらして深掘りする”と言っています。ずらすと課題解決から遠ざかりそうに思えますが、考え方をちょっと変える、それがずらして深掘りするということです。
CO2排出削減などサステナビリティに関わる課題解決は相反する要素のバランスを取る必要があり、従来の考え方・やり方を変えて解決へ迫る必要があります。変えていくアクションこそイノベーションであり、変えていくからこそ飛躍的に前進できると考えています。
変える必要があるものを見極め、必要な時は変えていく
業務に必要なマニュアルやルールには柔軟な思考を妨げることがあり、発想の自由を奪ってイノベーションを阻むことがあります。マニュアルにはいろいろな取り組みの基本方針などが書かれており、それらは経営や事業の軸として大事ですが、未来永劫、不変ではありません。不変なのは社是と経営理念だけで、マニュアルやルールは社是や経営理念を業務へ落とし込むためにあります。事業環境や市場、お客様の要望は常に変化しており、我々も年齢を含めて変化します。サステナビリティに関わる最近の変化は速く大きいため、従業員一人ひとりがイノベーティブに行動できるようマニュアルは変えて良いし変えなければサステナブルな企業になれないと考えています。
サステナブルな社会の実現を目指す取り組みはエンドレス
先の先、さらにその先まで思い描く

長期ビジョン「LSV 2030」は2021年4月に始動しまもなく中間点を過ぎますが、ゴールへ折り返すわけではありません。持続可能な社会は2030年以降もエンドレスで追求し続けるものであり、私はサステナビリティとは先の先さらにその先まで思い描くことだと捉えています。
当社は包装用ガムテープの製造・販売で創業し、シール・ラベル用粘着製品に事業の軸足を移し、さらに特殊紙や剥離紙・剥離フィルムにおいても技術を深掘りし事業を拡大してきました。特に粘着製品については、持ち前の技術開発力・製造力を駆使することで、シール・ラベルだけでなく自動車用やディスプレイ関連、半導体製造プロセスに関わる製品などに展開し、国内外のお客様から高い信頼を得てきました。この歩みは事業活動を通じ時代や市場に応じた社会的課題の解決に貢献してきた歴史であり、当社の成長と発展の基盤です。
事業を営む以上は社会の進む方向を見据えながら今やれることに取り組むのは当然であり、当社グループがこれまで培ってきた力を駆使することでサステナブルな社会の実現に挑み続けます。
当社グループの考え方を引き継いで実践していく
現時点では地球環境保全に対する気候変動の影響が非常に大きく、「今のままCO2を排出し続けてはいけない」との共通認識で社会が動いています。しかし10年後20年後、さらに影響の大きい新たな課題が出てくる可能性は否定できません。持続可能な社会実現の課題がはっきりしないのは当然で、ターゲットは動いていきます。たとえば2050年にカーボンニュートラルな社会を描いていますが、次期中期経営計画「LSV 2030-Stage 3」では積み上げた活動とその成果を踏まえてさらに先を描くことになります。
私の役割は当社グループに根付いている考え方に焦点を当て引き継ぐことであり、それを受け継ぎ実践していくことで、サステナブルな社会の実現に貢献できるものと考えています。

面白い、楽しいと感じたら、
ためらわずに一歩踏み出してみる
自分の感性を揺さぶるものに出会う機会を楽しむ
私が担当していた半導体関連の仕事が現在のような事業になるまで長い年月を要しましたが、楽しい面白いという感覚があり好きだったから途中で投げ出さず続けることができました。これは話していて楽しいとか考え方が面白いなどの率直な感覚であり、一人ひとりそれぞれ違って良いと思います。私自身、何事も正面からよく見て良いところをしっかり捉える姿勢を持ち続けることで育めた感覚だと考えています。
仕事であれほかのことであれ、楽しそうだなとか面白そうだなとか、どんな感覚でも良いから何かを感じたら体験してみる、一歩踏み出してみる、そうすれば自分自身の感性を揺さぶられるものが出てくると思います。従業員にはこの感覚を大切にしてほしいし、素直な感覚を持てるよう私自身がサポートし大切にできる会社であり続けたいと考えています。
社内外の声をしっかり受け止め活かしていく
サステナブルな社会の実現への貢献を目指した取り組みはまだパーフェクトではありませんが、重点テーマや施策を着実に推し進めたことで成果が出ています。一方、社内のいろいろなところへ顔を出して話を聞き、また株主・投資家の皆様をはじめとする社外とのミーティングに参加しアンケートにも目を通して、当社グループとしてやれることやるべきことがまだまだあると考えています。私はこれからも社内外の声をしっかりと受け止め、必要な手立てをスピーディーに実行していきます。
ステークホルダーの皆様には、これからも当社グループに関心や興味を持ち続けていただくとともに積極的な提言・助言をよろしくお願いいたします。


トップインタビューを終えて
~リンテックグループのサステナビリティ推進~
当社グループは、2030年3月期をゴールとした長期ビジョンLSV 2030を掲げ、サステナブルな社会の実現に向け各施策を推進しています。2024年度のLSV 2030-Stage 2のスタートに合わせて、トップメッセージにもある「取り組みやKPIは変化すべきもの」という視点およびStage 1の実績やダブルマテリアリティの考えを踏まえバリューチェーン分析などの4つの分析を行い、マテリアリティとKPIを見直しました。
2021年4月のLSV 2030のスタート以降、サステナビリティ委員会の下部委員会・分科会や担当部署が策定された計画に従い目標達成に向け各施策を実行してきました。Stage 2ではLSV 2030の実現をより確実なものにするため、サステナビリティ委員会において委員会・分科会それぞれの活動や施策が長期ビジョン、マテリアリティ(KPI)、中期経営計画のテーマと関連していることを改めて示し活動を開始しました。
これにより、施策の実行は手段であって「施策は何のため」「目標達成はどの重要課題を解決するか」という目的を持っていることを認識した活動が推進されると考えています。また、この認識を持って課題解決に取り組むことが、次の施策や目標策定、未達時の計画修正、計画の前倒しに不可欠であり、トップメッセージの「イノベーション」の話で触れられていた「ずらして深堀りする」ということにもつながります。
当社グループはこれまでの企業活動において省エネルギー、CO2排出量削減、環境配慮製品開発などの環境関連、人的資本経営に関わる働き方改革、人事や労働安全衛生関連などのさまざまな施策を実行しサステナビリティ経営を推進してきました。施策策定や制度改定には理由や目的があり、さらにこれまで積み上げてきた活動や実績の延長線上にあるのが現在のLSV 2030やマテリアリティ・KPIといえます。点で存在するこれまでの施策や活動をLSV 2030などと線でつなげていくことが、当社の環境や人的資本経営の方向性(戦略)を示すことそのものといえます。施策の実行や目標を達成することがどのような価値を創造し、当社グループが企業活動の源泉としている5つの資本(人的、知的、製造、社会関係、財務の各資本)を強化し、次の課題解決や価値の創造につなげていくかというストーリーでもあります。
また、当社グループおよび社会をサステナブルにしていくためには、グループ全従業員のモチベーションアップと繰り返し発信してきた会社の方針やあるべき姿にベクトルを揃えることが重要かつ必須です。2024年度で3回目となる従業員サーベイの結果でもエンゲージメントスコアが着実に変化しており、これまでの施策がモチベーションのアップ、部署内や部署間のコミュニケーションの活性化に寄与した結果を表しているといえます。
「企業文化として引き継いでいく考え方」「変化することを当たり前にする」というトップのメッセージや会社の方向性をグループ全従業員に繰り返し伝え、浸透させ、サステナビリティと事業を一体化した新たな価値を創造するためのストーリーを示すこと。そして、これらを土台として全従業員が「何のために」「いつまでに」「何をやるべきか」を「自分事」としてそれぞれの役割を果たすことにより、2030年のさらに先を考え行動し変化していくサステナブルな企業として、長期ビジョンの実現を通じサステナブルな社会の実現に貢献していきます。

執行役員
サステナビリティ推進室長
星 優
2025年8月29日